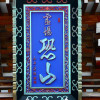photo credit: 永平寺 via photopin (license)
このブログの高野山の記事に海外からのアクセスが多いのは、高野山が世界遺産だから行ってみたいと思っている外人さんが多いから、と考えられるのだけれども、意外に永平寺にお伺いした時の記事も海外からのアクセスがボチボチあったりする。
何故永平寺の記事に?と思ったりもするけれども、若き頃のスティーブジョブズが、禅に傾倒して永平寺に出家しようと考えたというエピソードがあるので、日本に行くのならば永平寺に行きたい!と考える外国人の人が多いのも容易に想像出来る訳で。
そんなことを思いながら『ゼン・オブ・スティーブ・ジョブズ』という本を読んでみた。
小説かと思いきや、コミックだったのでちょっと拍子抜けしたのだけれど(笑)日本人の視点からの「禅」ではなくて、外人さんの目で見た「禅」というのは、こういうものなんだろうと思った。
私はアップル信者でもないし、iPadもiPhoneも持っていないので、何故人々がここまでアップル製品に夢中になるのかは、良く分からないというのが正直なところだったりする。
ただその人々が熱狂してやまないアップルの創業者である、スティーブジョブズに多大な影響を及ぼしたものが「禅」であるということが、とても意外に感じた。
けれども、この本(コミック)を読んで、全て余計なものをそぎ落とした結果、出来たものがアップル社の製品だということが分かった。
ラストの「書は人なり」と書かれた部分は、考えさせられた。
乙川弘文老師の最期は、池に落ちた娘を救おうとして娘ともども溺死してしまう、という、あっけないものであった。
そのシーンとジョブズが書をしたためているシーンがリンクして描かれているのだけれども、そこに書かれていた言葉の重みが胸に突き刺さった。
書は人なり
書道は、他のどんな芸術ともちがう
迷いが、すぐに形となって表れる
やり直しはきかない
その瞬間に書いたことが……
……すべて
残したいものを形にできればいいが
とにかく一回限りでやり直しはできないのだよ
同じような毎日を過ごしていると、ついつい気を抜いてしまったり、適当に済ませてしまうことも多かったりする。
けれども、このつまらない一日でも、毎日書をしたためているようなものだとしたら。
人生も、書も同じこと。
とにかく一回限りで、やり直しはきかない。
だからこそ、その瞬間、瞬間を生き切ることが大切なんだと。

ゼン・オブ・スティーブ・ジョブズ
集英社インターナショナル
売り上げランキング: 73,374