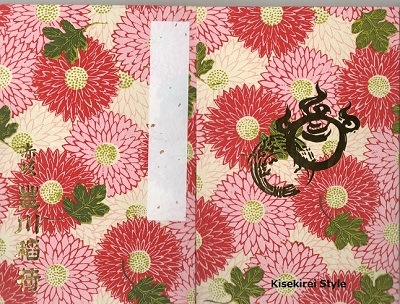
神社仏閣グッズを入れているケースを整理していたら、御朱印コレクターじゃないけれど、結構御朱印帳が溜まったなぁ、と改めて思ってしまったのでした。
これまで特に貰い方なども気にせずに、いろいろな神社仏閣で御朱印を頂いてきたのですが、いわゆる他の方を見ての、見様見真似でここまで来てしまった訳なので、一応御朱印関係の本でも読んでみようかと思い『御朱印ブック』という本を読んでみました。
神社、お寺の御朱印をいただくルール、や御朱印の保管場所などについても書かれていたけれど、私が実践してきた通りだったので、安心しました(笑)
神社、お寺の御朱印をいただくルール
1、 必ずお参りしてからいただきましょう

photo credit: kiffaanngissuseq via photopin cc
心をこめておまいりしたあと、御朱印をいただけるところへ向かうのが基本。
しかし広い境内のお寺や神社なら、先にご朱印帳をあずけ、参拝中に書いていただけるところもあります。
お参りしないで御朱印だけ貰う人なんて居るのかしらん?と思ってしまうけれど、居るんですよね、そういう人。私も見かけたことがあるけれど、見ていてあんまり気持ちが良いものじゃないなー、って。
2、御朱印帳&御朱印代は用意しておきましょう

photo credit: maccath via photopin cc
御朱印帳はおまいりの際に必ず持っていき、カバーつきのものなら開いて渡しましょう。御朱印代は、300円前後が一般的なので、お釣りのないよう小銭を用意しておくとスマートです。
御朱印代の300円に対して高額の紙幣(e.g.五千円札や一万円札)を出すのは控えた方が良いかと思います。
小銭が無いので両替してほしいという方も良く見かけるのですが、神社仏閣めぐりに欠かせないのは、小銭なので(←お賽銭やらお御籤やら引いていたらあっという間に小銭が無くなります)神社仏閣に行く前には、小銭を多めに用意しておくと良いと思います。
3、書いていただいている間は静かにしましょう

photo credit: Rev Stan via photopin cc
心をこめて書いてくださっている最中に、大きな声で関係のないおしゃべりに夢中になるのはマナー違反!まわりの人にも迷惑なうえ、なによりも書いてくださる人に失礼です。
これには激しく同意してしまうのでした。
友達同士で来ました~的な御朱印ガール?みたいな人たちは、何故か並んでいる時に、行った神社仏閣についてうんちくを垂れ流している場合が多いです。それを耳にする私は、内心(アホみたい)と思いつつ、聞いていないフリをしています(爆)
4、無理にお願いするのは控えましょう

住職さんや神職さんは、日々さまざまな仕事をこなしています。断られてしまったときも無理をいわないようにしましょう。
私も書ける人が不在ということで、御朱印を頂けなかったこともありますが、すべてはご縁だと思っているので、無理は言いません(笑)それこそコレクターだと無理を言ってしまうのかも知れませんが。。。
まとめ

この本にはその他にも、神社とお寺で御朱印帳はわけたほうが良いでしょうか?という質問に、お寺の方と神社の方が答える「御朱印集めの素朴な疑問にお答えします」というQ&Aがあったり、御朱印帳アイテムを手作りしてみよう!ということで、作り方が載ったりしています。
パラパラめくるだけでも、いろいろな神社仏閣の御朱印が見られて楽しかったです。
御朱印帳アイテム、ちょっと作ってみようかしらん?


